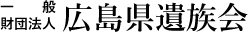令和7年 活動方針・事業計画
1 基本方針
日本遺族会では、国民の大多数が戦後生まれとなり、先の 大戦の記憶が消えようとしている状況に大いなる危機感を抱き、「戦没者遺族の辛く悲しい記憶は、二度と戦争の惨禍を繰り返さないための貴重な教訓である」との考えに基づき、草の根的に広がった「語り部」を確実に継承するため、全国的な組織化を令和5年度から3カ年計画で開始した。
本会に求められる「語り部」は、体験者故に語ることが出来る 戦中・戦後の実相を戦後生まれの青年部と共に、次世代へ伝承するものである。故に組織を次世代へ継承することは命題であり、本会は本年より組織強化を3カ年で計画している。
今一度、活動の原点に「戦争の犠牲を忘れさせないこと」すなわち「平和の語り部」に立ち返り、遺児の慰霊友好親善事業を 始めとする慰霊、遺骨収集、慰霊碑の適切な維持管理、遺留品の返還など全ての事業を戦争と平和を伝える「語り部」事業として伝承する努力を続けなければならないとされている。
当会においては、この趣旨に添いその実現に向けて、全力を挙げて取り組む。
英霊顕彰の根幹である内閣総理大臣の靖国神社参拝は、一部の近隣諸国に配慮し、参拝が途絶えていることは、誠に遺憾である。引き続き、総理、閣僚及び国民の代表たる国会議員の参拝定着化に向け一層の努力を傾注していかなければならない。
遺児が主体となっている遺族会は、護国神社の例大祭及び8月15日並びに市区町の慰霊祭には、今日の平和のために、国の礎となられたご英霊に思いをいたし、孫・ひ孫とともに参列し、末永く慰霊祭等が継続されるように努力する。
また、市区町の慰霊祭については、戦前の徴兵制度に地方自治体の果たした役割を考えると、首長が主体となって行うのが本来の姿である。
国内においても、先の大戦の記憶の風化が進みつつある今日において、県民が戦争の悲惨さ平和の尊さを忘れないためにも、戦争の風化を防ぎ、平和を語り継ぐことは、私たち遺族会に課せられた社会的責務であり、遺族会の創設理念である。
当会では、戦没者遺族に戦没者の人柄、思い出、足跡及び遺族の体験を語ってもらう県民向けの講演会として「戦没者を語る会」を開催し、内容を記録したDVDの配付及びホームページ等に掲載するなどして、戦争の悲惨さを広く県民に訴えている。
また、今後の本会の活動の中心となる「平和の語り部」事業を推進し、伝承していくため、親会・女性部・青年部が共に活動を行っていくことが必要である。
平和で豊かな時代に生まれた青年部世代への継承は容易ではない。県内各遺族会の戦没者の孫・ひ孫の中から役員後継者を選任して、県内各遺族会の中核部分の組織化を着実に推進しなければならない。
ついては、ここに令和7年度活動方針及び事業計画を策定し,懸案の解決に努める。
2 活動方針及び事業計画
(1) 英霊顕彰事業
我々が今日,平和と自由の恩恵を享受できるのは,戦没者の尊い犠牲によるものであることに思いをいたし,戦没者に対し国家,国民は尊崇と感謝の誠を捧げることを決して忘れてはならない。
①
総理,閣僚,多くの国会議員の靖国神社参拝が定着化するよう日本遺族会とともに運動を進める。また,引き続き英霊にこたえる会の事業に積極的に協力する。
②
首長である知事が護国神社の春秋の例大祭及び8月15日の日に参拝するように要請する。
③
昭和館,靖国神社遊就館の展示や巡回特別企画展により,戦中戦後の国民生活の労苦を後世代に伝え,若年世代に戦争の悲惨さと平和の尊さを訴える啓蒙活動に努める。
④ 地域慰霊祭及び平和祈願祭等の奨励・参列
戦没者遺族は一段と高齢化が進み,地域の慰霊祭・追悼式への参列者が減少している。各遺族会は,行政と連携しながら遺児・孫・ひ孫,配偶者及び遺族以外の者など,出来るだけ多くの人に参列していただき,式典が盛大に実施され,かつ,継続されるように努める。式典には案内により県会長または役員が出席し,追悼のことばを述べる。
⑤ 各遺族会の慰霊祭,追悼式への供物及び靖国神社,廣島・備後両護国神社へ玉串料等をお供えする。
各遺族会の慰霊祭等への供物は,1支部に年1回とする。
⑥
廣島護国神社及び備後護国神社主催の慰霊祭(県内戦没者73,293柱)に協賛し,県内遺族会から参拝した遺族に対して慰問品を配布する。
⑦ 沖縄「平和祈願大会並びに平和祈願慰霊大行進」への参加(一般財団法人 日本遺族会主催 県遺族会受付)
「慰霊の日」(6月23日)に沖縄県糸満市内で実施されるこの事業について,事前に各遺族会へ参加者募集の通知文を送付する。
⑧ 戦没者遺留品の返還に伴う調査事業
海外等に散逸する戦没者遺留品の返還に伴う調査事業については,日本遺族会が厚生労働省の指導のもとOBONソサエティーと連携し,実施されている。
日本遺族会から遺留品の持ち主または,その遺族の所在調査依頼があった場合には,該当遺族会は,関係遺族会員及び行政窓口を通じて積極的に聞き取りを行い,遺留品の早期返還を図る。
また,県内関係者の調査で不明なものについては,ホームページに掲載し,調査を継続する。
⑨ 慰霊碑等の保全事業
各遺族会で調査された慰霊碑等を随時,本会ホームページに継続して掲載する。また,慰霊碑の位置図及び修繕等の記録を追加して掲載する。
民間団体などが建立した慰霊碑は,県内に229基(調査済み)ある。高齢化で管理者がいなくなり,倒壊等の危険のある慰霊碑などについては,自治体が移設や撤去を行う際に国の補助金を充当しているが,今後,これらの登録された慰霊碑等については,管理者が高齢となり管理できない場合を考慮し,国や自治体が積極的に民間建立慰霊碑の維持管理に関与するように要請していく。
(2) 処遇改善運動の推進
高齢化著しい戦没者遺族にとって公務扶助料等は,生きてゆくための重要な糧となっているのは周知の事実である。しかし,国会において,野党議員から,公的年金引き下げに準拠すべきとの意見がある。戦没者遺族に対し支給される公務扶助料等の意義について,国家補償の理念で支給されるものであることを,国会議員に対して機会をとらえて広く知らしめる努力を引き続き行う。
① 全国戦没者遺族大会への参加
英霊顕彰の全国的な推進や戦没者遺族の福祉の向上を図るため,日本遺族会が主催するこの大会に役員等が参加し,地元国会議員に陳情活動を行う。
戦没者遺族に対する処遇改善は,国家補償の理念に基づき処遇改善がなされるよう,日本遺族会の要望事項の実現に向けて努力する。
② 特別弔慰金
継続・増額となった特別弔慰金について、対象遺族が速やかに受給できるよう努めるとともに,戦没者の孫,ひ孫等も支給対象となるよう,受給要件の緩和を引き続き、本部,支部一体となって国に強く求める。
また、未加入者の遺族会への加入を積極的に促すよう努める。
(3) 広報啓発事業
① 県遺族新聞を発行し,会員及び遺族に無料配布する。
県,各遺族会の活動状況,関係官庁の連絡事項,遺族の意見要望事項等を掲載し,会員間の情報交換及び連携を図る。
② 日本遺族会発行の遺族通信を会員に無料配布する。
日本遺族会の活動状況,遺族処遇改善の内容等並びに日本遺族会主催の各種事業の周知徹底を図る。
③ 「戦没者を語る会」の開催
第10回特別弔慰金の支給に当たり,付帯決議として,「先の大戦の記憶が風化しつつある現状に鑑み,当時の記憶及び教訓を次世代に継承していくため,学校教育の充実並びに啓発及び広報等の取組みの更なる強化を図ること」と決議されている。
このことから,県遺族会役員会・研修会等及び各遺族会役員会等に併せて,戦没者遺族に体験談及び戦没者の人柄,思い出,足跡を語ってもらう県民向けの講演会を実施し,内容をホームページに保存・普及させる。
④ 平和の語り部事業の推進
今後の遺族会活動の中心となるものであり、親会・女性部・青年部が共に活動していくことが必要であり、その担い手となる次世代の育成に取り組む。
⑤ ホームページ保守管理事業
「戦没者を語る会」の講演内容を収録するとともに日本遺族会及び当会の各種事業への申込書も入手できるなど,内容も充実してきた。
現在の収録内容は次のとおりであるが,必要に応じて拡充する。
- ア 本会の歴史(平成8年発刊の「㈶広島遺族会のあゆみ」 を収録)
- イ 本会の事業予定及びお知らせ等
- ウ 各支部一覧表及び実施事業
- エ 当年の事業計画
- オ 県内の慰霊碑(写真,建立年,戦没者氏名又は柱数,管理者等)各慰霊碑建立場所の位置図
- カ 日章旗等の戦没者の遺品を早期に遺族に返還するための遺品の写真,調査の必要事項等
- キ 戦没者を語る会の講演内容の録画(動画)
- ク 各支部の戦没者追悼式等の内容及び全国戦没者追悼式,沖縄ひろしまの塔追悼式の記念式典の内容
- ケ 広島県遺族会発行の機関紙
- ア 全国戦没者追悼式への参列(県の補助事業)
- イ 沖縄「ひろしまの塔」戦没者追悼式への参列(県の補助事業)
- ウ 遺児の慰霊友好親善 政府主催(政府補助事業)
- エ 戦跡慰霊巡拝(日本遺族会主催)
- オ 遺骨収集事業(日本戦没者遺骨収集推進協会主催)
- カ 慰霊巡拝事業(厚生労働省主催)
⑥ 社会奉仕活動への参加
戦没者遺族にとって相応しい社会奉仕活動(ボランティア,老人ホーム等の慰問)並びに北方領土返還要求運動広島県民会議が主催する大会及び街頭活動に参加する。
(4) 組織の拡充強化事業
本会の使命である,英霊顕彰と戦没者遺族の福祉の向上は,今後とも推進強化していかなければならない。
組織活動の維持には財政の確立と人材の確保が欠かせない。このためあらゆる方策を講じて,資金の確保と孫・曾孫の勧誘に努める。
①
各支部における会員の減少に伴い県遺族会への寄付金(分担金)の納入困難な状態となっているので,一般財団法人日本遺族会への分担金相当額に減額する。
②
特別弔慰金の継続・増額を契機ととらえ、各遺族会において未加入者の遺族会への加入を促す。
③
各遺族会において次世代後継者である「青年部」(戦没者の孫・曾孫等)の入会を進め,将来の世話役を早期に決定する。
④
日本遺族会及び当会の各種事業の参加者等に対し,もれなく会員とするように努力をする。
⑤
女性部は、研修会等を通じて情報収集に努めるとともに,各遺族会にあっては女性遺児の参加を積極的に進めるとともに,遺児の配偶者,孫,ひ孫の入会を促進し,後継者の育成に努める。
(5) 遺族対策(援護)
① 一般財団法人 広島県遺族会会長表彰
表彰規程に基づき,表彰審査委員会で認められた戦没者遺族及び功労者に対して表彰状及び感謝状を贈呈する。
また,上記被表彰者のなかから,日本遺族会長表彰,県知事表彰,厚生労働大臣表彰の被表彰者として推薦を行う。
② 遺族地区相談
遺族援護関係の法律は,毎年改正が行われ,その内容も複雑となっている。
各支部主催で開催される慰霊祭,追悼式に出来るだけ会長または役員が出席し,相談に応ずるとともに県本部でも援護の拡充整備,普及徹底のため遺族の相談に応じ,適切に受給権が行使されるように努める。
③ 全国戦没者追悼式への参列(県の補助事業)
県が窓口となっている国費参列団に加えて,広島県遺族会が募集した遺族会員が団体で参列する。
時期 8月15日 2泊3日
各遺族会の希望者 40名(会員・家族・孫・曾孫出席者については,県及び当会から補助金が支給される。)
④ 沖縄「ひろしまの塔」戦没者追悼式への参列(県の補助事業)
(広島県管理 南方諸地域で戦没された広島出身者 34,635柱が合祀されている。)
広島県主催の沖縄「ひろしまの塔」戦没者追悼式に参列する(県の補助事業)。今年は、知事及び議長が参拝される。
時期 6月上旬頃 2泊3日
各遺族会の推薦者 50名(会員・家族・孫・曾孫については,県及び当会から補助金が支給される。)
(6) 遺児の慰霊友好親善及び遺骨収集事業
① 遺児の慰霊友好親善 政府主催(政府補助事業)
戦没者の遺児も平均年齢が90歳近くになり,参加が困難となりつつある。引き続き各遺族会への通知と日本遺族通信の配布を通じて本事業の周知徹底を図り,参加者の増加に努める。
令和7年度実施地域
広域地域 1回 300名(予定)
①洋上慰霊
特定地域 2回 240名(予定)
①フィリピン1次 ②フィリピン2次
② 戦跡慰霊巡拝(日本遺族会主催)
昨年度に続き,青年部事業の一環として,国内での慰霊巡拝を含めて検討され,実施予定である。当会窓口で受付を行う。
③ 遺骨収集事業(日本戦没者遺骨収集推進協会主催)への参加
「一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会」が政府から委託を受け実施するこの事業について,事業概要の周知徹底を図り,遺児に加えて孫・曾孫の参加を促す。
令和7年度実施地域 17地域 (予定)
① フイリッピン ② 東部ニューギニア ③ ビスマーク・ソロモン諸島 ④ インドネシア ⑤ パラオ諸島 ⑥ マリアナ諸島 ⑦ トラック諸島 ⑧ マーシャル諸島 ⑨ ギルバート諸島 ⑩ ミャンマー ⑪ インド ⑫ バングラディシュ ⑬ ノモンハン ⑭ 硫黄島 ⑮ 沖縄 ⑯ その他南方地域 ⑰ 旧ソ連地域
参加方法は,当遺族会経由の日本遺族会への希望者の事前登録による。
④ 慰霊巡拝事業(厚生労働省主催)
国庫補助対象者は,戦没者の配偶者,父母,子,兄弟姉妹,参加遺族(子・兄弟姉妹)の配偶者,戦没者の孫,戦没者の甥・姪とされている。また,補助金は,旅費の3分の1相当額が交付される。
申し込みは,住所地の市,町窓口となる。
広島県社会援護課長から県内各市町長宛ての文書の写しを,当会から各遺族会へ通知し,周知を図る。
令和7年度政府主催・慰霊巡拝地域 10地域(予定)
① 硫黄島 ② フィリピン ③ 東部ニューギニア ④ パラオ諸島 ⑤ トラック諸島 ⑥ インドネシア ⑦ ミャンマー ⑧ 中国 ⑨ カザフスタン ⑩ ウズベキスタン
(7) 法人運営
- ① 理事会・評議員会(3月,6月)
- ② 常務理事会 年3回以上
- ③ 女性部長会議及び幹事会 年1回以上
- ④ 女性部研修会・青年部研修会等
- ⑤ 監査 年1回以上
- ⑥ 一般財団法人日本遺族会理事会(年2回),評議員会(年1回),女性部研修会,青年部研修会,事務局研修会